| 新しい地球像をもとめて[地球のからくり] |
| 1B03[ 近づいてみる ] |
 |
■近づいて見る
Mission to the Space
遠くの天体(てんたい)をよく見ることには、限界(げんかい)があります。それは、光は距離(きょり)が離れると弱(よわ)まっていくからです。光を弱めずに見るには近づけばよいのです。望遠鏡(ぼうえんきょう)を宇宙空間(うちゅうくうかん)に送りだすのとは違(ちが)った考えかたです。望遠鏡を宇宙空間に出しましたが、修理(しゅうり)や操作(そうさ)を考えると、できるだけ地球に近い方がよいのです。くわしく見るためには、私たちの「目」を遠くの天体に近づけるしかありません。私たちは分身(ぶんしん)を地球のかなたに送りはじめました。
写真 惑星探査機(わくせいたんさき)ボイジャー
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
 |
■探査機(たんさき)
地球以外の天体(てんたい)に近づいてみれるようになったのは1960年代に入ってからです。このころ、宇宙空間にロケットを打ち上げられるようになったのです。最初に宇宙から見た天体は地球でした。ついで月に無人(むじん)ロケットを打ちこみ、やがて1969年にはアポロ11号によって人類(じんるい)を月に送りこみました。つぎのターゲットは地球に近い星、火星(かせい)と金星(きんせい)、水星(すいせい)でした。やがて、目標(もくひょう)は遠くの惑星(わくせい)へと広がっていきました。今や、探査機は太陽系全体や、彗星(すいせい)にまで向かっています。よりよく知るために、さまざまな目的(もくてき)をもった探査機が送りこまれるようになったのです。
写真 惑星探査機(わくせいたんさき)バイキング
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
 |
■水星(すいせい)
軌道半径(きどうはんけい):5.8×107km、公転周期(こうてんしゅうき):88日、自転周期(じてんしゅうき):58.6日、平均半径(へいきんはんけい):2,439km、質量(しつりょう):3.3×1023kg、密度(みつど):5.4kg/cm3、表面温度(ひょうめんおんど):620K(絶対温度(ぜったいおんど))(昼)、100K(夜)
写真 水星(すいせい)
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
 |
■金星(きんせい)
軌道半径(きどうはんけい):1.1×108km、公転周期(こうてんしゅうき):225日、自転周期(じてんしゅうき):243.0日(逆行(ぎゃっこう))、平均半径(へいきんはんけい):5,988km、質量(しつりょう):4.9×1024kg、密度(みつど):5.4kg/cm3、表面温度(ひょうめんおんど):750K(地表)、 240K(雲)
写真 金星(きんせい)
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
 |
■火星(かせい)
軌道半径(きどうはんけい):2.3×108km、公転周期(こうてんしゅうき):687日、自転周期(じてんしゅうき):1.0日、平均半径(へいきんはんけい):3,388km、質量(しつりょう):6.4×1023kg、密度(みつど):3.9kg/cm3、表面温度(ひょうめんおんど):250K(表面)
写真 火星(かせい)
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
 |
■小惑星(しょうわくせい)
小惑星(しょうわくせい)は、半径(はんけい)の小さい天体(てんたい)のことです。火星(かせい)と木星(もくせい)の間にたくさんの小惑星があり、小惑星帯(しょうわくせいたい)とよばれます。
写真 小惑星(しょうわくせい)ガスプラ
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
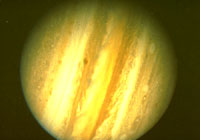 |
■木星(もくせい)
軌道半径(きどうはんけい):7.8×108km、公転周期(こうてんはんけい):4,333日、自転周期(じてんしゅうき):0.41日、平均半径(へいきんはんけい):69,953km、質量(しつりょう):1.9×1027kg、密度(みつど):1.3kg/cm3、表面温度(ひょうめんおんど):120K(雲)
写真 木星(もくせい)
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
 |
■土星(どせい)
軌道半径(きどうはんけい):1.4×109km、公転周期(こうてんしゅうき):7,840日、自転周期(じてんしゅうき):0.43日、平均半径:(へいきんはんけい)58,130km、質量(しつりょう):5.7×1026kg、密度(みつど):0.698kg/cm3、表面温度(ひょうめんおんど):90K(雲)
写真 土星(どせい)
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
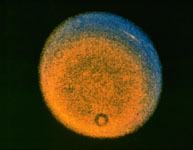 |
■天王星(てんおうせい)
軌道半径(きどうはんけい):2.9×109km、公転周期(こうてんしゅうき):30,689日、自転周期(じてんしゅうき):0.7日、平均半径(へいきんはんけい):25,200km、質量(しつりょう):8.6×1025kg、密度(みつど):1.3kg/cm3、表面温度(ひょうめんおんど):60K(雲)
写真 天王星(てんおうせい)
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
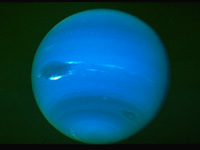 |
■海王星(かいおうせい)
軌道半径(きどうはんけい):4.5×109km、公転周期(こうてんしゅうき):60,182日、自転周期(じてんしゅうき):0.74日、平均半径(へいきんはんけい):24,623km、質量(しつりょう):1.03×1026kg、密度(みつど):1.7kg/cm3、表面温度(ひょうめんおんど):50K(雲)
写真 海王星(かいおうせい)
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
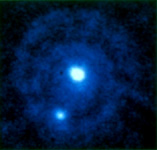 |
■冥王星(めいおうせい)
軌道半径(きどうはんけい):5.9×109km、公転周期(こうてんしゅうき):90,516日、自転周期(じてんしゅうき):6.4日、平均半径(へいきんはんけい):1,180km、質量(しつりょう):9×1021kg、密度(みつど):1.8kg/cm3、表面温度(ひょうめんおんど):0K(表面)
写真 冥王星(めいおうせい)
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
 |
■ハレー彗星(すいせい)
ハレー彗星(すいせい)は、74.7年ごとに太陽をめぐります。最近では1986年に出現(しゅつげん)しました。いびつな形(7×7×15km)をしたもので、岩石まじりの氷からできていることがわかってきました。
写真 ハレー彗星(すいせい)
|
| |
|
.関連項目: |
地球から見る |
| 地球の外から見る |
|
|
|
|
|
|
EPACS Museum of Natural History
EPACS 自然史博物館 |