折原貴道 (ORIHARA, Takamichi)

| 氏名 | 折原貴道 (ORIHARA, Takamichi) |
|---|---|
| 所属 | 動物・植物グループ 主任学芸員 |
| 専門 | 菌類 【菌類分類学、菌類系統学】 |
| 学位 | 博士(農学) |
| t_orihara@nh.kanagawa-museum.jp | |
|
きのこ、カビなど菌類について担当しています。中でも、地下生菌・シクエストレート菌(トリュフなど、地中や落ち葉の下にきのこをつくる菌類)の分類や系統、生物地理などの研究に力を入れています。2016年には、地下生菌を専門に扱う団体「日本地下生菌研究会」を立ち上げました。現在は、地下生菌だけでなく、さまざまな希少菌類の保全や、市民とともに進める菌類調査などにも積極的に取り組んでいます。
[Curriculum Vitae PDF file(193KB) in English] |
|
2024年5月12日 更新
資料収集(あつめる)
日本国内だけでなく、海外の研究者とも連携して、世界各地のきのこ類の標本を集めています。また、当博物館菌類ボランティアグループと協力して、博物館周辺(小田原市入生田)のさまざまな菌類を採集し、標本として保管しています。菌類の種数は全世界で約220万~1320万種とも推定されていますが、現在名前が付けられているのはそのうちわずか16万種弱です。私たちの身近な環境にも、多くの知られざる菌類が生育しています。標本の収集は、未知の菌類を知るための大事な一歩です。
また、主要な研究対象である、地下生菌の標本を日本全国から広く集め、日本の地下生菌標本コレクションの拠点を形成することを目指しています。地下生菌は一般的に採集が難しく、研究がとても遅れていますが、コレクションを充実させることで、地下生菌のさまざまな研究の進展に繋がれば、と考えています。

ヤミイロクヌギタケ Mycena nidificate Har. Takah.
小田原市入生田で最初に発見され、新種として記載された希少種.

ウスベニタマタケ Turmalinea persicina Orihara
国内のシイ・カシ林に発生するピンク色の地下生菌.2016年に新属・新種として記載されました。
調査・研究(しらべる)
1.地下生菌(シクエストレート菌)の系統分類
きのこ(子実体)を形成する菌類のうち、落ち葉の下や地中にきのこを形成するものを地下生菌といいます。高級食材として有名なトリュフの仲間も地下生菌に含まれます。地下生菌の多くは、きのこの内部に胞子をつくるため、自力で胞子を遠くへ散布することができません。そのため、昆虫、小型哺乳類などにきのこを食べてもらうことで胞子を散布していると考えられています。また、多くは球状のきのこを形成しますが、実は菌類の様々な系統から似たような形に進化してきたことが分かってきています。私は、これらの菌がどのような菌類から進化してきたのか(系統関係)を明らかにし、分類体系を構築・整理することを主要な研究テーマとしています。
地下生菌についての詳細は、[自然科学のとびら Vol.18, No.1, 2012](6.5MB)および日本地下生菌研究会ウェブページをご覧ください。


図1. ネズミツチダマタケ Rossbeevera griseovelutina Orihara 2011年に筆者により新種として発表された地下生菌です。ヤマイグチの仲間(図2)と共通祖先の地上生きのこ類から進化したと考えられています。

図3. 地下生菌、ガウチエリア属の一種Gautieria sp.(左)はホウキタケ型の地上生きのこ(右)の系統から進化したことが明らかになっています。
2.市民参加型調査に基づく多様な菌類の調査研究
当博物館には、老若男女問わず、菌類の関心を持つ人々が多く集まり、多様な活動がおこなわれています。特に、菌類分野の博物館ボランティア(菌類ボランティア)には、多数のアマチュア研究者・愛好家が在籍しており、毎月、博物館周辺の菌類(*)を採集・観察し、博物館標本として収蔵する活動を継続しています。2023年には、専門家の監修のもと、菌類ボランティアを中心とする一般市民のグループにより、博物館周辺のさまざまな菌類の詳細な観察記録をまとめた大型資料『新・入生田菌類誌』を作成、出版しました。プロの研究者と一般市民の双方が集う博物館ならではの取り組みとして、私は、このような市民参加型の菌類調査を率先して進めています。
*きのこ、地衣類、微小菌類、植物病原菌、変形菌など
研究例:
- 生命の星・地球博物館 入生田菌類誌調査グループ(編著),折原貴道(監修)(2023) 新・入生田菌類誌. 生命の星・地球博物館 入生田菌類誌調査グループ, 神奈川, 412 pp.
- 出川洋介・折原貴道 (2022) 菌類. 神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課・神奈川県立生命の星・地球博物館編, 神奈川県レッドデータブック 2022 植物編, pp. 380–425. 神奈川県, 横浜.
- 折原貴道,中村恭子,村田知章 (2017) 地域児童とともに進める、真鶴半島の大型菌類相調査と外生菌根菌に着目したクロマツ生育状況評価. 神奈川県立博物館研究報告 46: 7–23.

図4. 菌類ボランティア活動の様子
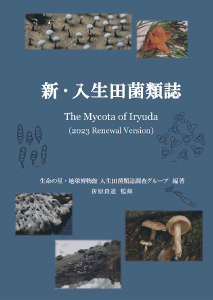
図5. 『新・入生田菌類誌』表紙
専門分野の論文および総説
-
高木 望, 陶山 舞, 佐藤大樹, 折原貴道 (2023) 日本で初めて検出されたブユ幼虫の腸内糸状菌Genistellospora 属(トリモチカビ門,ハルペラ目).神奈川自然誌資料 (44): 11–16.
-
Nagao H, Ohnishi W, Orihara T. (2023) Leaf blister on Leucothoe grayana var. venosa caused by an Exobasidium species. Bull. Kanagawa Pref. Mus. (Nat. Sci.) (52): 1–5.
-
畠山颯太, 折原貴道 (2022) ツチダンゴ属 Elaphomyces、特にE. granulatus およびE. muricatus をめぐる分類学史. Truffology 5 (2): 69–75.
https://jats-truffles.org/truffology/vol_5_2/truffology_vol5_art12/ -
Yamato M, Yamada H, Maeda T, Yamamoto K, Kusakabe R, Orihara T. (2022) Clonal spore populations in sporocarps of arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 32(5–6): 373–385.
https://doi.org/10.1007/s00572-022-01086-1 -
Orihara T, Castellano MA, Ohmae M, Kaneko Y, Hosaka K. (2022) Taxonomic re-examination and phylogeny of neglected Japanese black deer truffles, Elaphomyces miyabeanus and E. nopporensis. Truffology 5(1): 3–13.
https://jats-truffles.org/truffology/vol_5_1/truffology_vol5_art2/ -
折原貴道 (2022) 巻頭言: 日本地下生菌研究会会報『Truology』発刊5 周年に寄せて. Truffology 5(1): 1.(査読無)
https://jats-truffles.org/truffology/vol_5_1/ -
Orihara T, Healy R, Corrales A, Smith ME. (2021) Multilocus phylogenies reveal three new truffle-like taxa and the traces of interspecific hybridization in Octaviania (Boletaceae, Boletales). IMA Fungus 12, article no. 14.
https://doi.org/10.1186/s43008-021-00066-y
和文による論文紹介 -
中井 実, 大前宗之, 折原貴道 (2021) 植栽されたナルコユリを宿主とする日本新産種Stromatinia rapulum(キンカクキン科).日本菌学会会報 62: 51–55.
https://doi.org/10.18962/jjom.jjom.R02-11 -
Kinoshita A, Sasaki H, Orihara T, Nakajima M, Nara K. (2021) Tuber iryudaense and T. tomentosum: Two new truffles encased in tomentose mycelium from Japan. Mycologia 113(3): 653–663.
https://doi.org/10.1080/00275514.2021.1875709 -
Yamamoto K, Endo N, Ohmae M, Orihara T. (2021) Balsamia oblonga (Helvellaceae), a new species from a subalpine forest in Japan. Truffology 4: 1–7.
https://jats-truffles.org/truffology/vol_4/truffology_vol4_art1/ -
陶山 舞,高木 望,出川洋介,佐藤大樹,折原貴道 (2021) 神奈川県におけるフナムシ腸内寄生菌フナムシヤドリ(新称)Asellaria ligiae の生息状況. 神奈川自然誌資料 (42): 53–56.
-
折原貴道 (2020) ヤマイグチ亜科(イグチ科イグチ目)に含まれる日本産地下生菌の多様性と分類. 日本菌学会会報 61: 63–80.
https://doi.org/10.18962/jjom.jjom.R02-09 -
大前宗之,山本航平,折原貴道 (2020) Microstoma apiculosporum(チャワンタケ目ベニチャワンタケ科)の国内初記録. 日本菌学会会報 61: 27–32.
https://doi.org/10.18962/jjom.jjom.R01-10 -
折原貴道,山本航平,保坂健太郎 (2020) 『オオショウロ(イグチ目ショウロ科) の分布、系統および分類学的扱いについて』への訂正. Truffology 3: 45–46.
https://jats-truffles.org/truffology/vol_3/ -
畠山颯太, 折原貴道 (2020) 日本各地から60 年ぶりに発見されたアサヒヒメクロツチダンゴ. Truffology 3: 33–37.(査読無)
https://jats-truffles.org/truffology/vol_3/ -
折原貴道,保坂健太郎,畠山颯太,糟谷大河 (2020) 環境省レッドリスト掲載地下生菌(スナタマゴタケ、ハハシマアコウショウロ、シンジュタケ)の再探索と分布の現状について.Truffology 3: 17–27.
https://jats-truffles.org/truffology/vol_3/truffology_vol3_art3/ -
Yamamoto K, Sasaki H, Ohmae M, Orihara T. (2020) Leucangium microspermum: Re-examination of Japanese L. carthusianum reveals its taxonomic novelty. Truffology 3: 1–7.
https://jats-truffles.org/truffology/vol_3/truffology_vol3_art1/ -
Yamamoto K, Yasuda M, Ohmae M, Sato H, Orihara T. (2020) Isaria macroscyticola, a rare entomopathogenic species on Cydnidae (Hemiptera), is a synnematous form of Purpureocillium lilacinum (Ophiocordycipitaceae). Mycoscicnce 61: 161–164.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mycosci/61/4/61_MYC61160/_article/-char/ja/ -
Sulzbacher MA, Orihara T, Grebenc T, Wartchow F, Smith ME, Martín MP, Giachini AJ, Baseia IG. (2020) Longistriata flava (Boletaceae, Basidiomycota) – a new monotypic sequestrate genus and species from Brazilian Atlantic Forest. Mycokeys 62: 53–73.
https://doi.org/10.3897/mycokeys.62.39699 -
He M-Q, Zhao R-L, Hyde KD et al. (2019) Notes, outline and divergence times of Basidiomycota. Fungal Diversity 99: 105–367.
https://doi.org/10.1007/s13225-019-00435-4 -
Yamamoto K, Ohmae M, Orihara T. (2019) Metarhizium brachyspermum sp. nov. (Clavicipitaceae), a new species parasitic on Elateridae insects from Japan. Mycoscicnce 61: 37–42.
https://doi.org/10.1016/j.myc.2019.09.001 -
折原貴道 (2019) 昭和期に記載された稀産シクエストレート菌の実体解明と保全対策の再検討. IFO Research Communications 33: 193.(査読無)
-
Hosen MI, Zhong XJ, Gates G, Orihara T, Li TH. (2019) Type studies of Rossbeevera bispora, and a new species description within Rossbeevera from south China. Mycokeys 51: 15–28.
https://doi.org/10.3897/mycokeys.51.32775 - 折原貴道,山本航平,大場由美子,阿部晴恵 (2019) 伊豆諸島の地下生菌はいつ,どこからやってきたのか—海洋島の大型菌類の多様性解明と保全に向けた基礎的研究.自然保護助成基金成果報告書 25 周年特別記念号,181–190.
-
折原貴道(2019) トガサワラショウロRhizopogon togasawariana の和歌山県における初記録.Truffology 2: 18–19.(査読無)
http://jats-truffles.org/truffology/vol_2/ -
折原貴道,山本航平,保坂健太郎 (2019) オオショウロ(イグチ目ショウロ科)の分布、系統および分類学的扱いについて. Truffology 2: 10–17.
http://jats-truffles.org/truffology/vol_2/ -
Yamamoto K, Ohmae M, Orihara T. (2019) First report of a hypogeous fungus, Pachyphlodes nemoralis (Pezizaceae) from subalpine forest in Japan. Truffology 2: 1–5.
http://jats-truffles.org/truffology/vol_2/ - Hosaka K, Kobayashi T, Castellano MA, Orihara T. (2018) The status of voucher specimens of mushroom species thought to be extinct from Japan. Bulletin of the National Museum of Nature and Science. Series B, Botany 44(2) 53–66.
-
折原貴道,出川洋介 (2018) 御蔵島の地下生菌相の特徴. Mikurensis 7: 31–38.(査読無)
http://mikura-isle.com/pdf/mikurensis2018/31-38.pdf -
大前 宗之,山本 航平,折原 貴道 (2018) アカダマタケ(Melanogaster utriculatus)の分類学的扱いの変遷について. Truffology 1: 28–30.(査読無)
http://jats-truffles.org/truffology/vol_1/ -
山本航平,折原貴道 (2018) 日本産地下生菌の分類学的研究史. Truffology 1: 14–21.
http://jats-truffles.org/truffology/vol_1/ -
Orihara T. (2018) First report of a rare sequestrate fungus, Rossbeevera yunnanensis (Boletaceae, Boletales) from Japan. Truffology 1: 5–8.
http://jats-truffles.org/truffology/vol_1/ -
折原貴道 (2018) 日本地下生菌研究会の設立、および日本地下生菌研究会会報“Truffology”発刊を記念して―日本の地下生菌研究のこれまでとこれから―(巻頭言). Truffology 1: 2–4.(査読無)
http://jats-truffles.org/truffology/vol_1/ - 陶山舞,佐藤大樹,折原貴道 (2018) 入生田におけるアシマダラブユ幼虫腸内寄生菌の通年観察. 神奈川自然誌資料 39: 1–4.
- Oshima M, Tomida Y, Orihara T. (2017) A new species of Plesiosorex (Mammalia, Eulipotyphla) from the Early Miocene of Japan: first record of the genus from East Asia. Fossil imprint 73 (3–4): 292–299.
-
Orihara T, Smith ME. (2017) Unique phylogenetic position of the African truffle-like fungus, Octaviania ivoryana (Boletaceae, Boletales) and the proposal of a new genus, Afrocastellanoa. Mycologia 109 (2): 323–332.
http://dx.doi.org/10.1080/00275514.2017.1301750 -
折原貴道 (2017) 今関六也氏菌類画コレクションから明らかになった,きのこ分類学者としての伊藤篤太郎. 企画展『伊藤篤太郎生誕150年—初めて植物に学名を付けた日本人—』に関連する講演会(論文集)pp. 10–15. 名古屋大学博物館,名古屋.
http://www3.arkw.co.jp/nagoya-u/museum/event/special/2015/160204.html#relate - 折原貴道,中村恭子,村田知章 (2017) 地域児童とともに進める、真鶴半島の大型菌類相調査と外生菌根菌に着目したクロマツ生育状況評価.神奈川県立博物館研究報告 46:7–23.
- 矢野倫子,矢野清志,山本幸憲,折原貴道 (2017) 伊豆半島の変形菌相. 神奈川県立博物館研究報告 46: 25–38.
-
Kumar LM, Smith ME, Nouhra ER, Orihara T, Leiva PS, Pfister DH, McLaughlin DJ, Trappe JM, Healy RA. (2017) A molecular and morphological re-examination of the generic limits of truffles in the Tarzetta-Geopyxis lineage – Densocarpa, Hydnocystis, and Paurocotylis. Fungal Biology 121 (3): 264–284.
http://dx.doi.org/10.1016/j.funbio.2016.12.004 - 陶山舞,佐藤大樹,折原貴道 (2017) 本州初記録となるブユ幼虫の腸内糸状菌Simuliomyces microsporus(ハルペラ目)の神奈川県からの発見. 神奈川自然誌資料 38: 1–4.
-
Orihara T, Lebel T, Ge Z-W, Smith ME, Maekawa N. (2016) Evolutionary history of the sequestrate genus Rossbeevera (Boletaceae) reveals a new genus Turmalinea and highlights the utility of ITS minisatellite-like insertions for molecular identification. Persoonia 37:173–198.
http://dx.doi.org/10.3767/003158516X691212
和文による論文紹介 - 矢野倫子,矢野清志,山本幸憲,折原貴道 (2016) 日本初記録の2分類群を含む神奈川県鎌倉市広町緑地の変形菌相. 神奈川県立博物館研究報告 45: 69–79.
-
Orihara T, Ohmae M, Yamamoto K. (2016) First report of Chamonixia caespitosa (Boletaceae, Boletales) from Japan and its phylogeographic significance. Mycoscience 57: 58–63.
http://dx.doi.org/10.1016/j.myc.2015.08.005
和文による論文紹介 - 中島淳志, 折原貴道 (2015) ミカン果実上のアジア新産種Talaromyces cecidicolaおよびその基質依存的なシンネマの形態変化. 神奈川自然誌資料 36: 1–6.
- 矢野倫子,矢野清志,山本幸憲,折原貴道 (2015) 富士山静岡県域の変形菌. 神奈川県立博物館研究報告 44:49–70.
- 折原貴道 (2014) イグチ科シクエストレート菌未知系統の探索と分類、および進化的・地理的起源の解明. IFO Research Communications 28: 128.
- 矢野倫子,矢野清志,折原貴道,山本幸憲 (2014) 真鶴半島の変形菌相. 神奈川県立博物館研究報告 43: 67–71.
- 折原貴道,岡田豊太郎,大宮司俊彦,高木望 (2014) 神奈川県におけるショウロの発生状況. 神奈川県立博物館研究報告 43: 63–66.
- 保坂健太郎,井口潔,折原貴道 (2013) 明治神宮境内より採集された担子菌類. 鎮座百年記念第二次明治神宮境内総合調査報告書 pp. 125–134. (査読無)
- 佐藤大樹,折原貴道 (2013) ブユ幼虫の腸内寄生菌Pennella angustispora(ハルペラ目)の神奈川県初記録. 神奈川自然誌資料 34:21–23.
- 矢野倫子,矢野清志,山本幸憲,折原貴道 (2013) 逗子市神武寺の変形菌相継続調査―昭和天皇の採集氏を中心に―. 神奈川県立博物館研究報告 42: 13-22.
-
Orihara T, Smith ME, Ge Z-W, Maekawa N. (2012) Rossbeevera yunnanensis (Boletaceae, Boletales), a new sequestrate species from southern China. Mycotaxon 120: 139-147.
http://dx.doi.org/10.5248/120.139 -
Orihara T, Smith ME, Shimomura N, Iwase K, Maekawa N. (2012) Diversity and systematics of the sequestrate genus Octaviania in Japan: two new subgenera and eleven new species. Persoonia 28: 85-112.
http://dx.doi.org/10.3767/003158512X650121 - Yagame T, Orihara T, Selosse M-A, Yamato M, Iwase K. (2012) Mixotrophy of Platanthera minor, an orchid associated with ectomycorrhiza-forming Ceratobasidiaceae fungi. New Phytologist 193: 178-187.
-
Lebel T, Orihara T, Maekawa N. (2012) The sequestrate genus Rosbeeva T.Lebel & Orihara gen. nov. (Boletaceae) from Australasia and Japan: new species and new combinations. Fungal Diversity 52: 49-71.
[Lebel T, Orihara T, Maekawa N. (2012) Erratum to: The sequestrate genus Rossbeevera T.Lebel & Orihara gen. nov. (Boletaceae) from Australasia and Japan: new species and new combinations. Fungal Diversity 52: 73.] - 折原貴道, 前川二太郎 (2010) きのこ類の近年の分類体系について. 菌蕈 56 (11): 24-30.
- Orihara T, Sawada F, Ikeda S, Yamato M, Tanaka C, Shimomura N, Hashiya M, Iwase K. (2010) Taxonomic reconsideration of a sequestrate fungus, Octaviania columellifera, with the proposal of a new genus, Heliogaster, and its phylogenetic relationships in the Boletales. Mycologia 102 (1): 108-121.
- Orihara T, Kasuya T, Phongpaochit S, Dissara Y. (2008) Radiigera tropica (Geastraceae, Geastrales), a new species from a tropical rain forest of Thailand. Mycotaxon 105: 111-117.
- 大藪崇司, 折原貴道, 岩瀬剛二(2007)日本国内に植栽されたユーカリ樹木の生理生態と大型菌類の発生消長. 環境情報科学論文集21: 65-68.
- Kasuya T, Orihara T, Fukiharu T, Yoshimi S. (2006) A lycoperdaceous fungus, Arachnion album (Agaricales, Arachniaceae) newly found in Japan. Mycoscience 47: 385-387.
論文以外の学術的著作(抜粋)
-
折原貴道 (2023) かながわご当地菌類 ガイドブック(2023年度特別展展示解説書).第1章,第2章(部分執筆),第3章,第4章(部分執筆),第5章.神奈川県立 生命の星・地球博物館,神奈川.
-
生命の星・地球博物館 入生田菌類誌調査グループ(編著),折原貴道(監修)(2023) 新・入生田菌類誌. 生命の星・地球博物館 入生田菌類誌調査グループ, 神奈川, 412 pp.
-
折原貴道 (2022) きのこ好きのための地下生菌学入門. くさびら(神奈川キノコの会 会報)(44): 2–6.
-
出川洋介・折原貴道 (2022) 菌類. 神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課・神奈川県立生命の星・地球博物館編, 神奈川県レッドデータブック 2022 植物編, pp. 380–425. 神奈川県, 横浜.
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f12655/p1197000.html -
折原貴道 (2016) 第4章 菌類. 矢野興一編. 見る目が変わる博物館の楽しみ方—地球・生物・人類を知る. pp. 172–196, ベレ出版, 東京, 440pp.
https://www.beret.co.jp/book/44901 -
折原貴道(編)(2015)2015年度特別展展示解説書『生き物を描く~サイエンスのための細密描画~』,神奈川県立 生命の星・地球博物館,神奈川,119 pp.
学会発表(国際学会;招待講演を含む)
- Kinoshita A, Sasaki H, Yamamoto K, Ohmae M, Orihara T, Obase K, Yamanaka T, Yamada A, Nara K. (2019) Revisiting Japanese truffle phylogeny and diversity: possibilities for cultivation and edibility. The 10th International Workshop on Edible Mycorrhizal Mushrooms (IWEMM10), Suwa, Nagano, Japan, 21–25 Oct 2019.
- Orihara T. (2019) Unexpected cryptic species diversity of undescribed, white sequestrate Russula spp. (“Koishi-take”) found from Japan. Asian Mycological Congress 2019 (AMC2019), Tsu, Mie, Japan, 1–4 Oct 2019.
- Orihara T. (2019) Locally threatened mushrooms and truffles in Kanagawa Prefecture ― their current and future treatment. IUCN Red Listing of Fungi – A Practical Workshop, Asian Mycological Congress 2019 (AMC2019), Tsu, Mie, Japan, 1 Oct 2019.
- Orihara T. (2018) Recent mycological activities in Kanagawa Prefectural Museum of Natural History (KPM). MSA-MSA Kanto Branch-MST joint excursion, KPM, Odawara, Kanagawa, 9 Dec 2018.
- Sato H, Suyama-Watanabe M, Orihara T, Degawa Y. (2018) Species of Harpellales recorded in Iriuda, Odawara Kanagawa Prefecture, Japan. MSA-MSA Kanto Branch-MST joint symposium, KPM, Odawara, Kanagawa, 8 Dec 2018.
- Sugimoto I, Suyama-Watanabe M, Orihara T. (2018) Activities of the Volunteer Group of Mycology, Kanagawa Prefectural Museum of Natural History. MSA-MSA Kanto Branch-MST joint symposium, KPM, Odawara, Kanagawa, 8 Dec 2018.
- Orihara T, Ohmae M, Yamamoto K, Degawa Y. (2018) Aspergillus becomes a truffle — enigmatic, bright yellow, hypogeous ascomata found from Japan. 11th International Mycological Congress (IMC11), Puerto Rico Convention Center, San Juan, Puerto Rico, 16–21 July 2018.
- Orihara T. (2017) Phylogeography of sequestrate fungi in Leccinoideae (Boletaceae) — a possibility of recent transoceanic dispersal. Asian Mycological Congress 2017 (AMC 2017), Tan Son Nhat Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam, 10–13 Oct. 2017.
- Yano M., Yano K., Yamamoto Y., Yano T, Orihara T. (2017) Myxomycetes Biota on the Southern Slope of Mt. Fuji. 9th International Congress on the Systematics and Ecology of Myxomycetes (ICSEM9), Tanabe, Wakayama, Japan, 18–23 Aug. 2017.
- Orihara T, Trappe JM, Castellano MA, Claridge AW. (2015) Multigene analyses unveil the phylogenetic position of the Australasian sequestrate provisional genus, “Pogisperma” (Boletaceae, Boletales). Asian Mycological Congress 2015 (AMC 2015), Goa University, Goa, India, 7 Aug. 2015. *Poster Presentation Award (2nd prize) 受賞.
- Hosaka K, Kasuya T, Orihara T, Nam K-O. (2015) Endangered or not - a case study on a presumably threatened species of truffle-like fungus from the oceanic islands in Japan. Asian Mycological Congress 2015 (AMC 2015), Goa University, Goa, India, 10 Aug. 2015.
- Orihara T. (2014) Recent progress in systematics of Leccinum-related sequestrate fungi (Boletaceae, Boletales). Special seminar at Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming, Yunnan, China, 18 Aug. 2014.
- Orihara T. (2014) Island phylogeography of truffles: incredibly high genetic diversity of Octaviania subg. Parcaea (Boletaceae) in the Japanese Archipelago. 10th International Mycological Congress (IMC10), Bangkok, Thailand, 4–8 Aug. 2014.
- Orihara T, Smith ME. (2013) Unique phylogenetic position of an African sequestrate fungus, Octaviania ivoryana, within Boletaceae (Boletales, Agaricomycotina). Asian Mycological Congress 2013 (AMC2013), China National Convention Center, Beijing, China, 19–23 Aug. 2013.
- Orihara T, Lebel T, Ge, Z-W, Smith ME, Maekawa N. (2013) Phylogeny and systematics of the sequestrate basidiomycete genus, Rossbeevera and allies (Boletaceae, Boletales). Mycology Colloquium in the FUNNZ 2013 Foray, Matawai, New Zealand, 15 May 2013.
- Sato H, Degawa Y, Orihara T. (2012) Gut-Living Fungi of Aquatic Insects In Japan: Harpellales (Zygomycota) Collected in 2011-2012. The First Symposium of the Benthological Society of Asia. Matsumoto, Nagano, Japan, 11–14 June 2012.
- Orihara T, Lebel T, Smith ME, Ohmae M, Maekawa N (2011) Systematics of Leccinum-related sequestrate fungi (Boletaceae) and variability of minisatellite-like insertion within the nuc-rDNA ITS region. Symposium at Asian Mycological Congress 2011 (AMC2011), University of Incheon, Incheon, Korea, 7 Aug. 2011.
- Orihara T, Okamoto K, Ohmae M, Maekawa N. (2010) Demystifying Phylogeny and Diversity of the Sequestrate Genus, Chamonixia in Japan. 9th International Mycological Congress (IMC9): The Biology of Fungi. Edinburgh, Scotland, UK, 5 Aug. 2010.
- Orihara T, Ohmae M, Shimomura N, Okamoto K, Yamato M, Iwase K, Maekawa N. (2009) Diversity and phylogeny of the sequestrate fungi related to Leccinum (Boletaceae) in Japan. Oral presentation. Asian Mycological Congress 2009. 18 Nov. 2009, National Museum of Natural Science, Taichung, Taiwan.
- Orihara T, Shimomura N, Yamato M, Iwase K, Maekawa N. (2009) Species diversity of the sequestrate genus, Octaviania in Japan revealed by molecular phylogenetic and ultrastructural studies and its evolutionary inference. International Conference on Fungal Evolution and Charles Darwin: From Morphology to Molecules. p. 28, Sirindhorn Science Home, Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand, July 2009.
- Orihara T, Yamato M, Ikeda S, Iwase K. (2007) What is Japanese “Hydnangium carneum” ―a proposal of a new sequestrate genus in Russulaceae and first finding of true H. carneum from Japan. Abstracts of the Asian Mycology Congress (AMC2007), p37, Parkroyal Penang, Penang, Malaysia, Dec. 2007.
- Orihara T, Yamato M, Ikeda S, Iwase K. (2007) Taxonomical reevaluation of two sequestrate (truffle-like) fungi, Octaviania columellifera and “Japanese O. asterosperma” (Boletales, Basidiomycota) based on morphological characterization and molecular phylogenetic analyses. The 4th International Joint Symposium between Korea and Japan “The Recent Status and Perspectives of Agricultural Environment and Biotechnology”, p250, Tottori University, Tottori, Japan, Nov. 2007.
- Iwase K, Orihara T, Oyabu T, Ikeda Y, Yamato M, Kurusu T, Ono Y. (2006) Adaptation of introduced exotic tree, Eucalyptus, to Japanese environment. Proceedings of the International conference on Ecological Restoration in East Asia 2006, p44, Osaka, Japan, June 2006.
- Orihara T, Sawada F, Ikeda S, Yamato M, Iwase K. (2005) Taxonomical reconsideration of Octaviania columellifera (Japanese name, jagaimo-take) and its phylogenetic relationships to Boletaceae. Proceedings of the MSA/MSJ joint meeting 2005, p176, Hilo, Hawaii, USA, Aug. 2005.
- Goto Y, Ando Y, Maruyama K, Sasaki H, Masai T, Orihara T, Shimono Y, Fukiharu T, Osaku K. (2005) Poisonous mushrooms in Japan: their taxonomy, toxicology and folklore. Proceedings of the MSA/MSJ joint meeting 2005, p117, Hilo, Hawaii, USA, Aug. 2005.
学会・研究会における発表(国内学会;過去5年間)
- 折原貴道・松尾 歩・山本航平・大前宗之・保坂健太郎・陶山佳久 (2024) 地下生菌はいかにして海洋島へ分布を広げるのか—伊豆・小笠原諸島における研究から. 2024年3月19日,第71回 日本生態学会大会 自由集会「日本から発信する島嶼生物学5」,横浜国立大学,横浜.
- 折原貴道・山本航平・金子義紀・岩間杏美 (2024) イッポンシメジ属のセコチウム型菌から検出されたアテリア目菌類. 2024年2月17日,日本地下生菌研究会2024年度総会・講演会,東京.
- 畠山颯太・山本航平・金子義紀・折原貴道 (2024) 国産褐色系ツチダンゴ属 (sect. Elaphomyces) の多様性紹介. 2024年2月17日,日本地下生菌研究会2024年度総会・講演会,東京.
- 折原貴道 (2023) 東京都新島村でのVisositunica radiata(アツギケカビ科)の発生の確認.日本地下生菌研究会2023年度講演会(オンライン開催).
- 折原貴道・大前宗之・畠山颯太・山本航平 (2023) ツチダンゴ属Malacodermei 節の分子系統と日本における種多様性. 2023年5月28日, 一般社団法人日本菌学会第67回大会,熊本(ハイブリッド開催).
- 折原貴道 (2023) 『新・入生田菌類誌』のご紹介.2023年4月28日,日本菌学会関東支部2023年度年次大会,三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center,横浜.
- 山田洋輝・前田太郎・山本航平・日下部亮太・折原貴道・大和政秀 (2022) アーバスキュラー菌根菌Redeckera spp.の胞子果内胞子の遺伝構造. 2022年12月10日, 菌根研究会2022年度大会(JCOM2022), 北海道大学農学部,札幌.
- 大和政秀・山田洋輝・前田太郎・山本航平・日下部亮太・折原貴道 (2022) アーバスキュラー菌根菌Rhizophagus irregularis, Diversispora epigaeaの胞子果形成胞子の遺伝構造. 2022年8月28日,一般社団法人日本菌学会第66回大会(オンライン開催).
- 折原貴道・山本航平・橋本 陽・大熊盛也・畠山颯太・出川洋介 (2022) 不完全菌Synnematomyces capitatus の系統的位置とアリによる栄養繁殖体の散布. 2022年8月27日,一般社団法人日本菌学会第66回大会(オンライン開催).
- 折原貴道 (2022) きのこ好きのための地下生菌学入門. 2022年5月29日,神奈川キノコの会令和4年度記念講演会,平塚,神奈川(招待講演).
- 折原貴道 (2022) 地下生菌の系統と多様性,国内での研究動向. 2022年3月6日,日本植物分類学会第21 回大会 公開シンポジウム「地中のきのこ×菌根」,オンライン開催.
- 折原貴道 (2021) 地下生菌の系統分類と進化,および国内における研究動向. 2021年11月13日,JCOM2021 菌根研究会2021 年度大会,つくば農林ホール(筑波産学連携支援センター内),つくば,茨城(ハイブリッド開催;オンライン参加;招待講演).
- 大和政秀・山田洋輝・前田太郎・山本航平・折原貴道(2021)アーバスキュラー菌根菌Rhizophagus irregularis とDiversispora epigaea の胞子果はクローン胞子によって構成される. 2021年11月13日, JCOM2021 菌根研究会2021 年度大会, つくば農林ホール(筑波産学連携支援センター内),つくば,茨城(ハイブリッド開催).
- 折原貴道・大前宗之・山本航平 (2021) 綴れ状最外皮を有するツチダンゴ類Elaphomyces mutabilis 複合種群の日本における種多様性.2021年8月23–29日,一般社団法人日本菌学会第65回大会(オンライン開催).
- 大前宗之・山本航平・星野 保・折原貴道 (2021) えぞ雷丸病菌の分類学的位置.2021年8月23–29日,一般社団法人日本菌学会第65回大会(オンライン開催).
- 大坪 奏,折原貴道 (2021) 昭和期に菌類画に描かれた未記載きのこ類-今関六也氏菌類図譜より.2021年8月23–29日,一般社団法人日本菌学会第65回大会(オンライン開催).
- 折原貴道 (2021) 日本菌学会会報(日菌報)の新たな出版方針について.自由集会1「日本菌学会の定期刊行物リニューアル」,2021年8月24日,一般社団法人日本菌学会第65回大会(オンライン開催).
- 折原貴道・中島稔・山本航平・大前宗之・畠山颯太・大塚健祐. (2020) 国内ユーカリ植栽地から発生が確認された南半球原産の地下生菌3種について.2020年6月20日,一般社団法人日本菌学会第64回大会,大阪市立自然史博物館,大阪(新型コロナウイルス感染症拡大のため大会は中止、発表は有効).
- 折原貴道・佐々木廣海・大前宗之・石庭寛子. (2020) 福島原発事故後の森林環境における地下生きのこ類発生状況調査. [Current occurrence of truffles and truffle-like fungi in forests near the Fukushima nuclear power plant accident] 2020年3月11日,放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究拠点 2019年度フラッシュトーク,web会議形式.
- 折原貴道 (2019) 過去に札幌周辺から記載された幻の地下生菌について. 2019年9月22日,日本地下生菌研究会第4回観察会(情報交換会),北海道大学,札幌,北海道.
- 折原貴道,Rosanne Healy, Matthew E. Smith (2019) 日本及び北米産ホシミノタマタケ属菌の未同定種3種の分類と種間交雑の可能性.一般社団法人日本菌学会第63回大会,秋田県立大学,秋田,2019年5月25–26日.
- 木下晃彦・佐々木廣海・折原貴道・中島 稔・奈良一秀 (2019) 大型胞子を形成する2種のトリュフ、Tuber ochraceumとTuber tomentosum. 一般社団法人日本菌学会第63回大会,秋田県立大学,秋田,2019年5月25–26日.
- 山本航平・大前宗之・折原貴道 (2019) ツチカメムシタケ(Isaria macroscyticola Kobayasi)の分類学的検討.一般社団法人日本菌学会第63回大会,秋田県立大学,秋田,2019年5月26日.
- 大前宗之・折原貴道 (2019) キリノミタケ科に含まれる日本産2 稀産種の系統分類.一般社団法人日本菌学会第63回大会,秋田県立大学,秋田,2019年5月26日.
- 細野天智・大前宗之・山本航平・折原貴道・出川洋介・逢沢峰昭・大久保達弘 (2019) 日本新産の好蘚苔類性チャワンタケ目ピロネマキン科菌について.一般社団法人日本菌学会第63回大会,秋田県立大学,秋田,2019年5月26日.
- 保坂健太郎・南京沃・折原貴道・大前宗之・山本航平 (2019) 小笠原産の謎の「絶滅種」ハハシマアコウショウロの正体.一般社団法人日本菌学会第63回大会,秋田県立大学,秋田,2019年5月26日.
- 折原貴道 (2019) イグチ類地下生菌の系統分類とその多面的展開(日本菌学会奨励賞受賞講演). 一般社団法人日本菌学会第63回大会,秋田県立大学,秋田,2019年5月25日.
- 折原貴道 (2019) 南方熊楠が遺した地下生菌図譜に描かれた種の実体.日本地下生菌研究会第3回総会・講演会, 国立科学博物館植物研究部棟, つくば, 茨城,2019年2月3日.
受賞
- 日本菌学会奨励賞.折原貴道(2019)研究題目:イグチ類地下生菌の系統分類とその多面的展開. 一般社団法人日本菌学会, 2019年2月8日(授賞式:2019年5月25日) .
- 第4回 勝本賞. 平成29年度日本菌学会関東支部年次大会, 玉川大学, 2017年4月15日(神奈川県立生命の星・地球博物館菌類ボランティアグループとしての受賞; 代表:折原貴道)
- 神奈川県教育委員会職員功績賞(個人) 折原貴道(2016)イグチ科地下生菌に関する研究に対する表彰. 神奈川県庁, 2016年3月30日.
- Poster Presentation Award, 2nd prize. Orihara T, Trappe JM, Castellano MA, Claridge AW. (2015) Asian Mycological Congress 2015 (AMC 2015; アジア菌学会議2015), Goa University, ゴア, インド, 2015年10月7日.
- NIOC賞 谷亀高広, 折原貴道, Marc-André Selosse, 大和政秀, 岩瀬剛二 (2011) 名古屋国際蘭会議 (NIOC). 2011年3月11日.
- The Best Student Poster Presentation Award. Orihara T, Shimomura N, Yamato M, Iwase K, Maekawa N. (2009) International Conference on Fungal Evolution and Charles Darwin: From Morphology to Molecules. Thailand Science Park, タイ王国, 2009年7月11日.
- 学生優秀発表賞 折原貴道 (2007) 日本菌学会第51回大会, つくば, 2007年5月27日.
研究助成金獲得状況
-
科研費 基盤研究 (C)(基礎生物学:生物多様性・分類)2022年4月–2025年3月(予定)
研究課題:「地下生菌ノアの方舟仮説」の検証―海洋島への菌類移入メカニズムの解明― -
令和2年度花博自然環境助成(入生田菌類誌調査グループとしての助成)2020年4月–2023年3月
課題:市民参加型調査に基づく大規模な地域菌類誌の出版 -
科研費 挑戦的萌芽研究(分担;中区分38:農芸化学およびその関連分野)2019年7月–2023年3月
研究課題:「アーバスキュラー菌根菌胞子果の同定分類と有性生殖の探索」 -
2019年度放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究拠点 重点共同研究 2019年6月–2020年3月
研究課題:福島原発事故後の森林環境における地下生きのこ類発生状況調査 -
科研費 若手研究 (B)(基礎生物学:生物多様性・分類)2017年4月–2021年3月
研究課題:空飛ぶ地下生菌仮説の検証—菌類の分生子に着目した,島嶼系統地理の新たな展開 -
公益財団法人発酵研究所 平成29年度一般研究助成 2017年4月–2019年3月
研究課題:昭和期に記載された稀産シクエストレート菌の実体解明と保全対策の再検討 -
公益財団法人自然保護助成基金 第27期(2016年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド特定テーマ助成「島の自然環境について基礎的調査」2016年10月–2018年8月
研究課題:伊豆諸島の地下生菌はいつ,どこからやってきたのか—共生菌類相に着目した,海洋島の森林保全へのアプローチ -
科研費 基盤研究 (C) (分担;農学:森林圏科学) 2016年4月–2018年3月
研究課題:日本国内の林地にみられるアーバスキュラー菌根菌群集に関する研究 -
科研費 若手研究 (B) (基礎生物学:生物多様性・分類) 2013年4月–2016年3月
研究課題:島嶼における系統地理から探る、きのこ類の収斂的な地下生化の起源 -
公益財団法人発酵研究所 平成24年度一般研究助成 2012年4月–2014年3月
研究課題:イグチ科シクエストレート菌未知系統の探索と分類、および進化的・地理的起源の解明 -
特別研究員奨励費(日本学術振興会 特別研究員DC1) 2009年4月–2011年3月
研究課題:地下生担子菌類香気成分の繁殖生態学的意義の解明と系統進化・分類学への適用
所属学会および研究会
- 一般社団法人 日本菌学会 (2019–20年度 代議員、幹事[庶務担当];2021–22年度 理事[日本菌学会報編集責任者];2023–24年度 理事[庶務担当])
- 日本地下生菌研究会(2016– 会長、事務局、総会・年次大会担当;2016–2020 編集・出版統括;2021– 編集委員)
- 日本菌学会関東支部 (2013–22年度 企画幹事 [菌類観察会担当])
- 米国菌学会 (Mycological Society of America)
- 日本進化学会
- 菌学若手の会
- 神奈川キノコの会、菌類懇話会、関西菌類談話会 など
展示(みせる)
担当した主な展示
令和5(2023)年度 特別展 かながわご当地菌類展 2023年7月15日~11月5日
これまでの活動の集大成として、神奈川県やその周辺から新種発表された菌類のほか、県内で絶滅のおそれのある希少種や、古くから利用されてきた菌類など、かながわらしい「ご当地菌類」を多数展示しました。また、このような菌類の調査・研究に、多くの一般市民が関わっていることも紹介しました。
令和2(2020)年度 企画展 かながわ発 きのこの新種展 2021年3月23日~5月23日
主担当として、神奈川県産のものを中心に、近年新種として発表された、多数のきのこの標本や、新種の発表に至るまでのプロセスや博物館での活動についての展示を行いました。
平成27(2015)年度 特別展 生き物を描く~サイエンスのための細密描画~ 2015年7月18日~2015年11月3日
昆虫担当学芸員の渡辺とともに、さまざまな生物画を、科学における重要性に着目して集めた特別展を、主担当の一人として企画・開催しました。また、本特別展の展示解説書の編集・構成も担当しました。

今関六也氏および本郷次雄氏の菌類画コレクションの展示準備の様子

特別展『生き物を描く~サイエンスのための細密描画~』の展示ブース
平成23(2011)年度 博物館ミニ展示 菌類のミクロワールド 2011年11月30日~2012年3月9日
博物館菌類ボランティアグループの方々の協力のもと、普段私たちの目では見えない菌類の微小な世界を再現しました。菌類がつくり出す胞子など様々な組織の模型を、同縮尺のアリと大きさを比べられるようにし、実際の大きさをイメージできるよう工夫しました。
教育・普及(つたえる)
普段あまり触れる機会のないカビやキノコについて、自然の中での役割や特徴などを学ぶための講座を開催しています。また、菌類の世界の面白さ、奥深さを伝えるさまざまな講座・講演会を館内外で行っています。講座・講演会に限らず、菌類に関する質問や研究の相談などを随時お受けしておりますので、ご遠慮なくメール・電話でお問い合わせください。
2024年度開催予定の当博物館主催講座
きのこさがし 2024年7月21日(小中学生向け)
きのこの観察と同定 2024年10月6日
2019年度開催の当博物館主催講座
きのこさがし 2019年7月26日(小中学生向け)
秋のきのこの観察と同定 2019年9月8日 など
2018年度開催の講座
きのこさがし 2018年7月27日(小中学生向け)
日本菌学会主催・当博物館共催 高校生のための菌類講座「博物館で学ぶ菌類学入門」2018年8月26日
秋のきのこの観察と同定 2018年10月7日 など
2017年度開催の講座
きのこさがし 2017年7月15日(小中学生向け)
秋のきのこの観察と同定 2017年10月1日 など
2016年度開催の講座
菌学事始め 2016年5月14–15日(担当:大坪・折原)
きのこさがし 2016年7月17日(小中学生向け)
秋のきのこの観察と同定 2016年10月2日 など
2015年度開催の講座
身近なカビの実験と観察 2015年8月
きのこの観察と同定入門 2015年10月
菌学事始め 2015年11月 など
2014年度開催の講座
菌学事始め中級編 2014年7月 (* 初級編は大坪学芸員が分担 [2014年5月])
秋のきのこ観察講座 2014年10月 など
2013年度開催の講座
菌学事始め中級編 2013年6月 (* 初級編は大坪学芸員が分担 [2013年5月])
味噌づくりの現場を見に行こう 2013年7月
秋のきのこ観察講座 2013年10月
2012年度開催の講座
菌学事始め中級編 2012年6月
夏休み菌類観察会~きのこ・カビ・変形菌を調べよう~ 2012年7月
秋のきのこ観察講座 2012年10月
2011年度開催の講座
菌学事始め 入門編 2011年6月
身近なカビの実験と観察 2011年8月
菌学事始め 初級編 2012年1月 など
新しい菌類分類体系の普及
菌類の分類体系は、以前は形態的な特徴に基づいて整理されていました。しかし、1990年代中ごろから、DNA情報に基づいて系統関係を調べる研究が盛んになり、21世紀に入って、形態に基づいたこれまでの分類体系が大きく変更されました。私は、国内の研究者やアマチュア愛好家と共同で、このような菌類の新しい分類体系を広く一般に普及する取り組みを率先して行っています。
関連業績(抜粋)
- 折原貴道, 長沢栄史, 細谷剛, 小林久泰 (2010) 2009年度日本菌学会菌類観察会で採用した新しい分類体系について. 日本菌学会ニュースレター 2010-1: 6-8.
- 折原貴道, 前川二太郎 (2010) きのこ類の近年の分類体系について. 菌蕈 56 (11): 24-30.
- 折原貴道 (2012) きのこの形に秘められた進化の歴史. 第101回サロン・ド・小田原講演会, 神奈川県立生命の星・地球博物館, 神奈川.
- 折原貴道 (2013) “新しい”菌類分類体系ができるまで. くさびら(神奈川キノコの会 会報)35: 3-8.
学芸トピックス
学芸員の活動成果や、メディアに取り上げられた際の情報を紹介しています。

